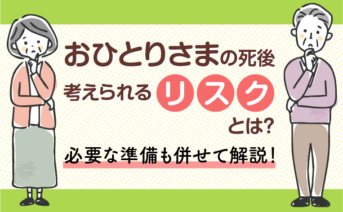死後事務手続きは専門家に代行してもらえる?依頼先やサービス内容を解説!
公開日: 2025年04月21日
更新日: 2025年04月21日
- 身元保証
- 葬儀・供養

逝去された方がいると、葬儀・供養の手配や、生前に暮らしていたお部屋の片付けなど、さまざまな手続きが生じます。このような亡くなった後に発生するさまざまな事務手続き(死後事務)は、従来は遺されたご家族が行うことが一般的でした。
しかしながら、核家族化や少子高齢化が進む現代において、生涯独身のおひとりさまや、一人暮らしをしているご高齢者も珍しくはありません。死後事務手続きはごく個人的な情報を扱うことになりますし、非常に多くの時間や手間がかかりますので、誰にでも気軽に依頼できるものではなく、お困りの方も少なくないでしょう。
死後事務手続きでお困りのご高齢者は、死後事務手続きの代行を専門家に依頼することがおすすめです。こちらでは、死後事務手続きをどこに頼めばよいかお困りの方に向けて、依頼先やサービス内容についてご紹介いたします。
おひとりさまのご高齢者はもちろん、ご親族はいるものの遠方に暮らしているなど死後事務手続きを任せることができない方や、お子様やご親族に手間をかけさせたくないとお考えの方も、ぜひ参考になさってください。
死後事務として行うべき主な手続き内容

死後事務は、お亡くなりになった直後から発生し、すべて完了するまでに多くの時間を要します。まずは、死後事務としてどのような手続きを行わなければならないのか、確認しておきましょう。
関係者への連絡
入院先の病院や入居先の施設等でご本人がお亡くなりになった際、ご親族等へご逝去の旨を連絡する必要があります。
葬儀や納骨などの手続き
お亡くなりになってすぐに手配しなければならないのが葬儀・供養です。葬儀を執り行うためには、葬儀の形式や規模、宗派、参列者としてお呼びする方の範囲、葬儀社の選定など、さまざまな内容を決める必要があります。
また、納骨方法も、お墓へ遺骨を納める埋葬をはじめとして、永代供養や樹木葬、海洋散骨など、さまざまな手法があります。
家賃や医療費などの精算
生前に暮らしていたお部屋の家賃の支払いや、医療費・入院費の精算、入居していた高齢者施設等の精算など、さまざまな費用の支払いや退去手続きが発生します。
行政関連の手続き
死亡届・国民健康保険資格喪失届・介護保険資格喪失届などの提出、年金の受給停止手続きなど、お亡くなりになった後は各種行政手続きが必要です。
お部屋などの清掃や家財道具の処分、デジタル遺品の処理
生前に暮らしていたお部屋の片付け、清掃、家財道具の撤去や処分はもちろんのこと、近年ではパソコン内のデータ消去やSNSのアカウント削除など、デジタル遺品の処理を必要とされている方も増えています。
残されるペットのお世話
ペットと共に暮らしている方は、お亡くなりになった後のペットの引き取り先を決めておくことも大切です。
ペットを引き継いでもらいたい人や団体をあらかじめ決め、必要に応じて飼育費用も準備し、お亡くなりになった後に引き継ぎ手続きを代行してくれる人も探す必要があります。
このように、お亡くなりになると数多くの手続きを行わなければならず、中には複雑な手続きを要する場合もあります。
死後事務に不慣れな一般の方が個人的に対応するには、非常に大きな負担となりかねません。多くの労力がかかることから、最後まで手続きしてもらえず、ご本人の希望どおりの死後事務が実現されないリスクもあります。
それゆえ、死後事務を依頼する際は信頼のおける人を選ぶことが重要です。
死後事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」
死後事務をご家族以外の第三者に依頼するのであれば、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。死後事務委任契約を結ぶことによって、第三者が死後事務手続きを代行する権限を証明することができます。
死後事務を依頼するご本人を「委任者」、死後事務を請け負う人を「受任者」といいます。
死後事務委任契約で依頼するサービス内容は、委任者の希望に合わせて決めることができます。信頼のおける方を委任者に選び、ご自身の希望をしっかりと反映させた死後事務委任契約を結びましょう。
死後事務手続きを代行してくれる専門家とは

死後事務では法的な手続きが必要となるケースもあるため、法律に精通した士業の専門家に依頼することがおすすめです。士業の専門家もさまざまで、それぞれ専門とする職務内容は異なります。
ご自身にとってどのような死後事務手続きが必要となるかを吟味し、誰に依頼すれば死後事務手続きを滞りなく進めてもらえるか考えていきましょう。
行政書士
行政書士は、主に行政手続きを法的にサポートする専門家で、書類作成業務や申請手続きの代行、必要書類の収集代行などを行う、いわば書類を扱うプロです。
ご高齢者が亡くなると、死亡届の提出や年金の受給停止手続きなどの行政手続きが必要となります。行政書士であれば、法律に従い、さまざまな事務手続きを正確かつ迅速に進めてくれるでしょう。
司法書士
司法書士も行政書士と同様に法律に関する事務手続きに対応しますが、司法書士は不動産登記に関する専門家であることが特徴です。
亡くなった方が不動産を所有していた場合には、法務局にて名義人死亡による所有権移転の登記申請が必要となります。司法書士は、ご本人に代わって法務局に対する申請書類の作成業務や、申請の代行に対応してくれます。
また、家庭裁判所での手続きが必要となった際は、申立て書類の作成代行など、申立てをお手伝いすることも可能です。
税理士
相続が発生した際、遺産額によっては相続税申告が必要となるケースもあります。税理士は税務の専門家として、納めるべき税金の計算や申請書類作成の代行など、税金に関する複雑な手続きに対応します。
税理士によっては、法人を対象として法人税の業務をメインに行うなど、相続税申告以外を専門としていることもありますので、税理士に依頼する際には専門分野についてもよく確認し、相続税に精通した税理士に依頼するとよいでしょう。
弁護士
弁護士は、法律や裁判に関する専門家であり、ご本人の代理人となることができます。
死後に発生した相続において、財産を巡り相続人同士の争いが生じると懸念される場合には、事前に弁護士に相談することも一つの方法です。
調停や裁判にまで発展しない場合でも、弁護士であれば法的な手続きに幅広く対処してもらえるでしょう。
金融機関
士業の専門家ではありませんが、銀行など金融機関によっては、死後事務サポートを行っているところもあります。
葬儀・供養の手配や家財道具の処分など、死後事務を行うためには費用がかかるため、生前のうちに死後事務に要する費用を「預託金」として、死後事務の委任先に預けることになります。預託金はそれなりの金額になりますので、死後事務の委任先が金融機関であれば、預託金の管理も安心です。
契約内容によっては、死後事務管理費用として、ご契約~お亡くなりになるまでの間に年間手数料が毎年継続して発生するケースもありますので、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。
生前から死後事務代行手続きまで一貫して任せられる身元保証団体に依頼するのがおすすめ
死後事務手続きは専門家に依頼することがおすすめとお伝えしましたが、「選択肢が多すぎる!結局誰に何を頼めばいいの?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。おひとり身のご高齢者の皆様にとって、将来のために備えておくべき対策は数多くありますので、混乱されることや、煩わしく感じられることもあるでしょう。
身元保証相談士協会では、おひとり身のご高齢者の将来を丸ごとサポートするため、生前の身元保証はもちろんのこと、死後事務代行手続きまでしっかりと対応させていただきます。各士業の専門家と連携し、ご高齢者の皆様のあらゆる不安を解消する体制を整えておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
ご高齢者の皆様の将来への不安を解消し、余生を「いきいきわくわく」とお過ごしいただくために、私ども身元保証相談士協会が力を尽くします。
身元保証や死後事務代行手続きについてお悩みやご不安がある方にむけて、身元保証相談士協会では初回完全無料の相談の場をご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
皆様のお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、サポート内容や費用など、わかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
全国93拠点の会員が
あなたの安心の身元保証をサポート
まずはお気軽にご相談ください。
地域の身元保証相談士
選びを手伝います
- 身元保証相談士協会では、行政書士・司法書士・税理士・介護事業者・葬儀など関連する事業者で連携して対応しております。